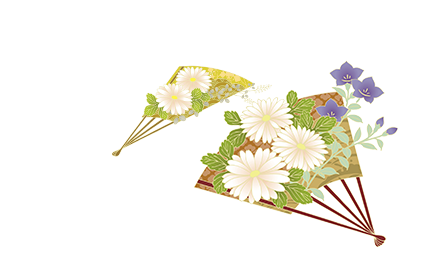名刀に関する知識をまとめました。
人々を魅了してやまない刀剣のなかには、「名刀」と呼ばれている刀が存在しています。「織田信長」「豊臣秀吉」などの著名な戦国武将も、数々の名刀を収集していました。
「名刀を知る」では、「日本刀の最高傑作」「最強の切れ味の刀剣」をはじめとした刀剣の知識はもちろん、刀の魅力と名刀が観られる博物館・美術館もご紹介。刀の知識を身に付けたい方の他、実際に刀を鑑賞してみたいという方にもおすすめです。
古来より日本刀は、その美しさから、武具としてだけでなく、祭神具や贈答品、家宝としても扱われてきました。日本刀の価値は、その切れ味の鋭さや使い勝手の良さなど、武具としての評価以外にも、美しさや技巧などの芸術的な観点、由緒や伝来などの歴史的な側面からも評価されます。「最高傑作」と呼ばれる日本刀にはどのようなものがあるのか、最高傑作と呼ばれ、現在でも名高い日本刀を観ていきましょう。
刀剣ワールド財団には、太刀をはじめ、打刀、短刀、脇差など、様々な種類の日本刀が、時代を問わず所蔵されています。刀剣ワールド財団が所蔵している日本刀のなかでも、特に人気のある上位15位の日本刀を、ランキング形式で順番に観ていきましょう。
「天下三名槍」(てんがさんめいそう)とは、日本で最も高名な3本の「槍」(やり)のことです。それは「日本号」(にほんごう/ひのもとごう)、「御手杵」(おてぎね)、「蜻蛉切」(とんぼきり)のこと。この3本の槍のどこがどう傑出して天下三名槍と言われるようになったのでしょうか。3本それぞれの姿や形、歴代の持ち主や槍を作刀した刀工などを詳しくご紹介します。
「神代三剣」(かみよさんけん)とは、「日本三霊剣」(にほんさんれいけん)とも言い、日本で神話の時代から伝えられている3本の剣のことです。それは「天十握剣」(あめのとつかのつるぎ:十拳剣[とつかのつるぎ])、「天叢雲剣」(あめのむらくものつるぎ:草薙剣[くさなぎのつるぎ])、「布都御魂剣」(ふつのみたまのつるぎ)。まさに、神の代わりとなるほどの強い霊力を備えていた3本の霊剣について、神話とともに詳しくご紹介します。
「三日月宗近」(みかづきむねちか)は、平安時代中期に刀工「宗近」(むねちか)によって鍛えられた太刀(たち)です。本太刀は日本で最も美しい刀剣と謳われ、「天下五剣」(てんがごけん)にも選ばれているなど誰もが認める名刀。その最大とも言える見どころのひとつが「号」(ごう)の由来にもなった、刀身に浮かぶ三日月形の「打除け」(うちのけ)です。「天下五剣・三日月宗近の解説」では、昨今ゲームや漫画などの影響で人気が高まっている刀剣、三日月宗近の歴史と刀身(とうしん)の解説を行っています。 天下五剣 YouTube動画
「鬼丸国綱」(おにまるくにつな)は、鎌倉時代の刀工「国綱」(くにつな)によって鍛えられた太刀(たち)です。鬼を斬った伝説をはじめ、室町幕府を開いた「足利尊氏」(あしかがたかうじ)が所有した伝説を持ちます。または、誰もが知る戦国武将である「豊臣秀吉」、「徳川家康」などの手にも渡りました。刀剣愛好家をはじめ若い世代に人気の刀剣、鬼丸国綱の歴史と刀身の解説を行っています。 天下五剣 YouTube動画
「童子切安綱」(どうじぎりやすつな)は、平安時代中期の刀工「安綱」(やすつな)によって鍛えられた太刀(たち)です。鬼退治や狐憑きを治すなど、多くの逸話を持つ童子切安綱は、足利将軍家から豊臣家、徳川家のもとを渡り歩いた来歴を持つ刀剣。「天下五剣・童子切安綱の解説」では、「天下五剣」(てんがごけん)のなかでも最高峰とされる、童子切安綱の歴史と刀身の解説を行っています。童子切安綱 YouTube動画
「大典太光世」(おおでんたみつよ)は、平安時代末期の刀工「光世」(みつよ)によって鍛えられた太刀(たち)です。本太刀は足利将軍家や「豊臣秀吉」、「前田利家」(まえだとしいえ)を祖とする加賀藩(現在の石川県)の藩主である前田家への伝来など、多くの著名人に関する逸話を持つ名刀。「天下五剣・大典太光世の解説」では、刀工・光世の傑作として「天下五剣」(てんがごけん)に選ばれている大典太光世の歴史と刀身(とうしん)の解説を行っています。天下五剣 YouTube動画
「数珠丸恒次」(じゅずまるつねつぐ)は、鎌倉時代初期の刀工「恒次」(つねつぐ)によって鍛えられた太刀(たち)です。名刀の多くが、持ち主である武士とのつながりによって物語や逸話を作り上げ価値を高めていきましたが、数珠丸恒次は僧とのかかわりが深い異色の刀剣。その代表的な所有者は、「日蓮宗」(にちれんしゅう)の開祖「日蓮」(にちれん)です。「天下五剣・数珠丸恒次の解説」では、「天下五剣」(てんがごけん)のなかでも戦いの逸話を持たない、数珠丸恒次の歴史と刀身の解説を行っています。天下五剣 YouTube動画
日本刀は、その特性から「折れず・曲がらず・よく切れる」武器として、実用に優れた点が評価されている他、見た目の類稀なる美しさが世界中で評価されています。その美しさから、古来、刀には不思議な力が宿ると考えられており、神様の依り代となったり、名刀に触れた者は魅入られてしまうと言われたりしているのです。なかでも、古くから伝来した刀は様々な人の手に渡り、多くの逸話や伝説が残されてきました。逸話や伝説のある刀とそのエピソードを紹介します。
日本刀は一般的に、茎(なかご:日本刀の持ち手部分)に刻まれた銘と日本刀の種類を組み合わせたものが名称とされていますが、「へし切長谷部」や「三日月宗近」などに代表されるように、なかには固有名が付けられているものも存在します。日本刀の別名である号と名物とはどのようなものなのかを説明。また、「名古屋刀剣博物館 名古屋刀剣ワールド」(愛知県名古屋市)が所蔵する、号のある日本刀や名物の日本刀を紹介します。
刀剣について学んでいると、「業物」(わざもの)や「位列」(いれつ)という単語がよく登場することに気が付きます。業物とは最強の切れ味を誇る刀剣を鍛えた刀工の称号のこと。位列とは、「技量別の刀工ランキング」と言う意味を持つ刀剣用語のことで、業物位列に選定された刀工の日本刀は古くから重宝されてきました。業物と位列それぞれの概要をご紹介します。
江戸時代、人体を用いて刀剣の「試し斬り」を行った人物がいました。それが、「人斬り浅右衛門」と呼ばれた「山田浅右衛門」(やまだあさえもん)。山田浅右衛門はひとりの人物の名ではなく、死刑執行をかねて刀剣の試し斬りを生業とした「山田家」の当主が代々名乗った名前です。山田浅右衛門の概要と江戸時代に行われていた試し斬りの方法、そして試し斬りの記録を示す「截断銘」(せつだんめい/さいだんめい)とは何かをご紹介します。
甲冑に身を固め、日本刀を携えて敵に立ち向かう、そんな合戦シーンをテレビドラマや映画で観たことがあるという方は多いのではないでしょうか。江戸時代に登場した浮世絵にも、日本刀を振るう甲冑武者の姿は数多く描かれてきました。ここでひとつの疑問がわいてきます。はたして、日本刀で甲冑を切ることはできるのか、ということです。日本刀が甲冑に対して有効であったのか、鉄砲や弓矢、槍(やり)など他の主要武器との比較も含めてみていきましょう。また甲冑武者を相手にしたときの戦い方についても言及します。
日本刀は、数ある刀剣類のなかでも最も見た目が美しいと評される刀です。また、漫画やゲームが好きな人であれば、「最強の武器」としての日本刀に大きな魅力を感じ、美術館などに赴いてその刀身(とうしん)を観るだけでもテンションが上がります。そして、日本刀の魅力はそれだけではありません。刀身をじっくり観れば、1振1振の形状が違ったり、その表面に美しい模様が付いていたりすることに気が付きます。人びとが日本刀に魅了される理由とは何か。日本刀の魅力を各部位の特徴と共にご紹介します。